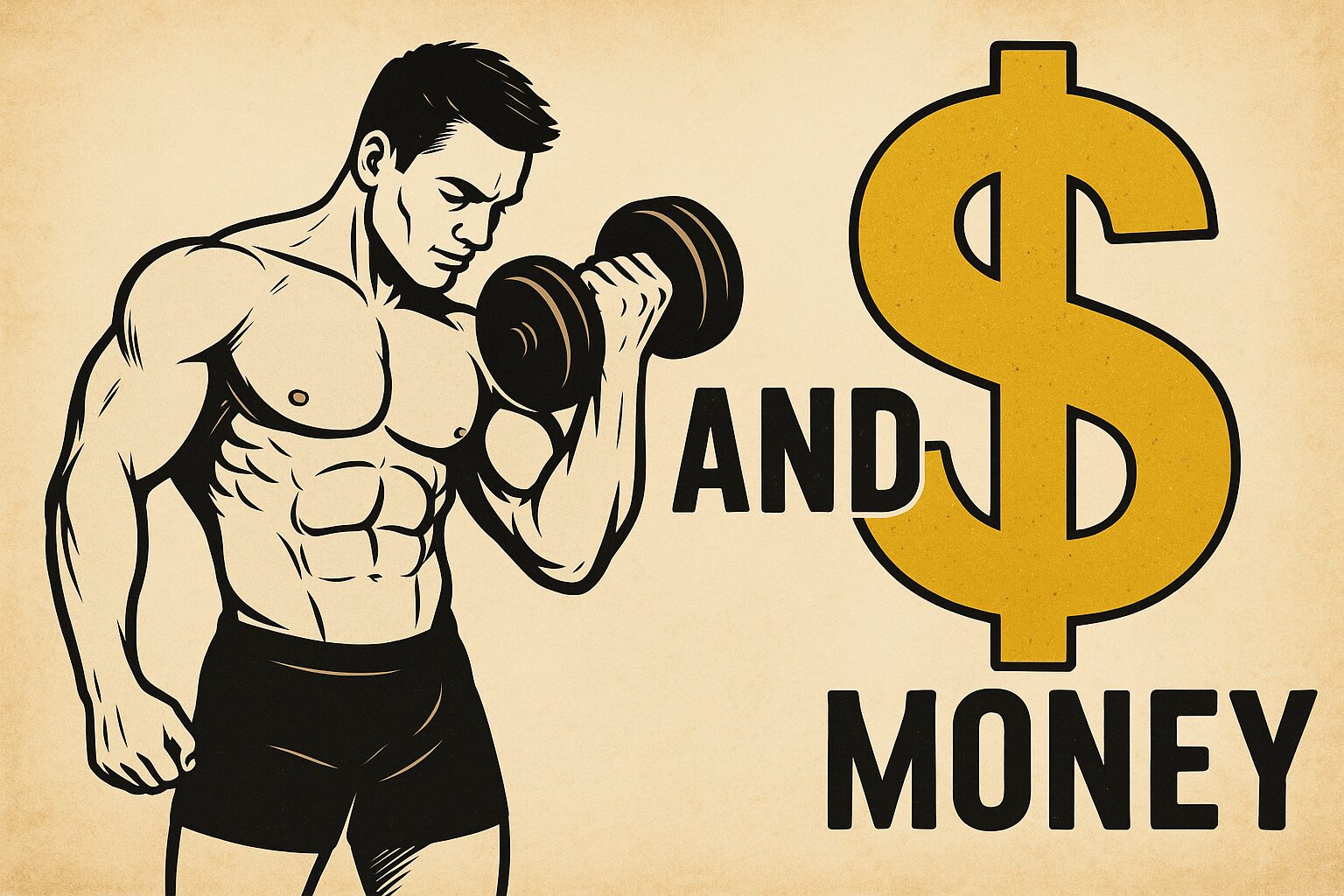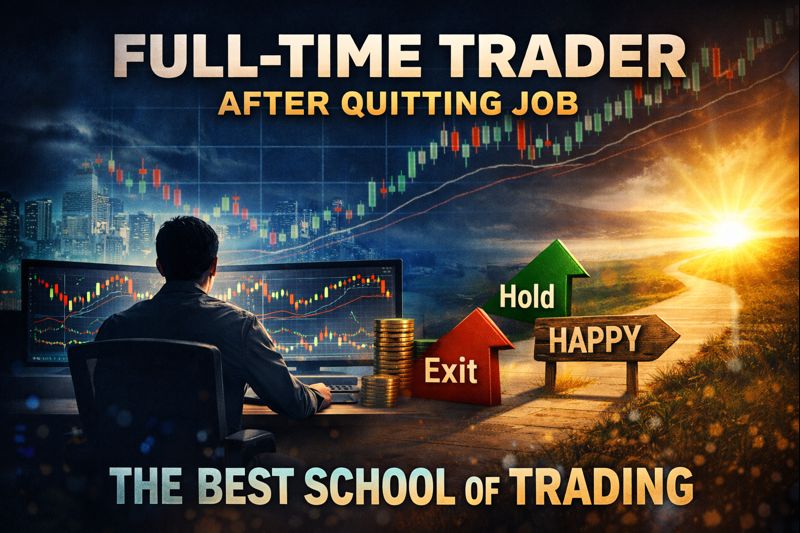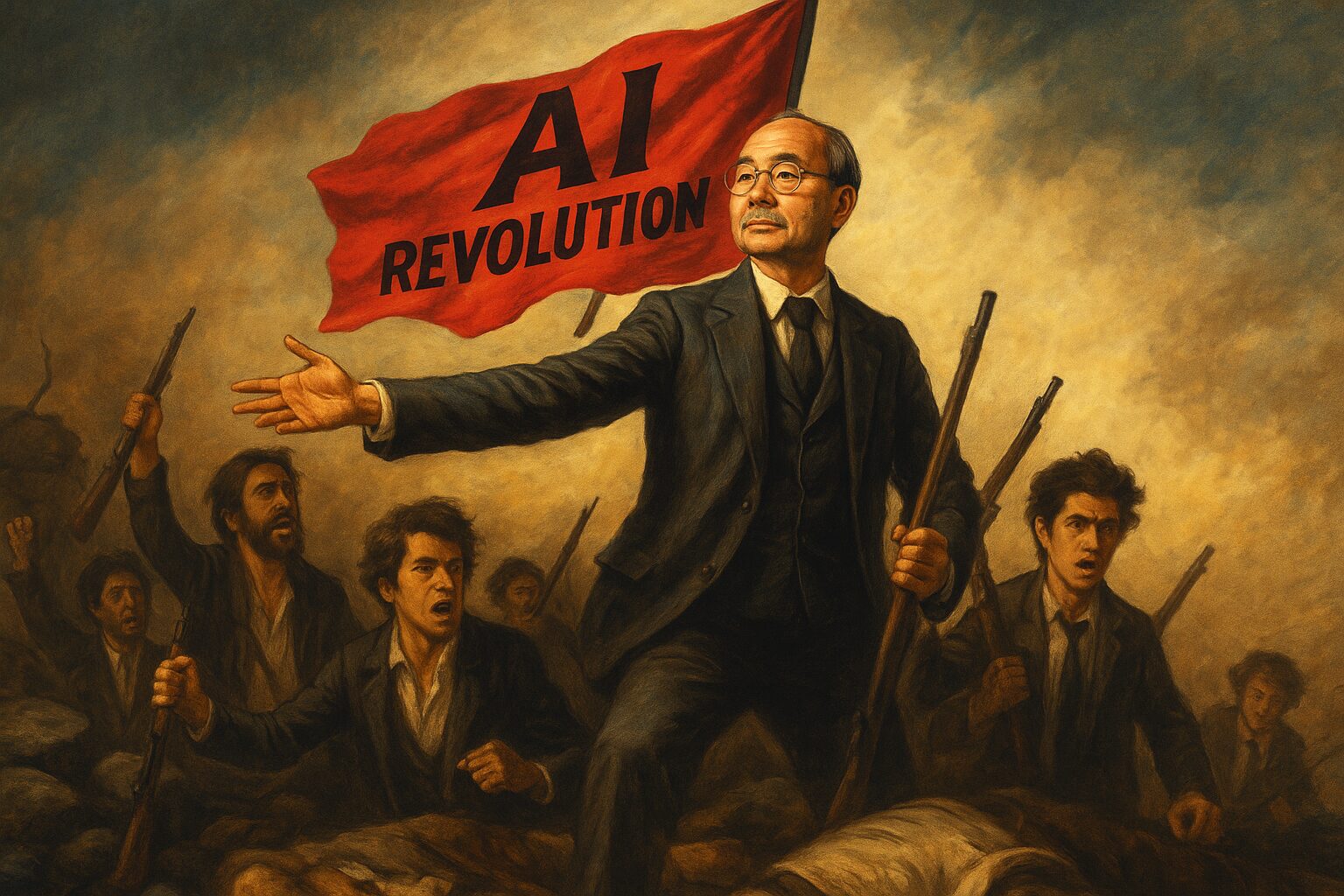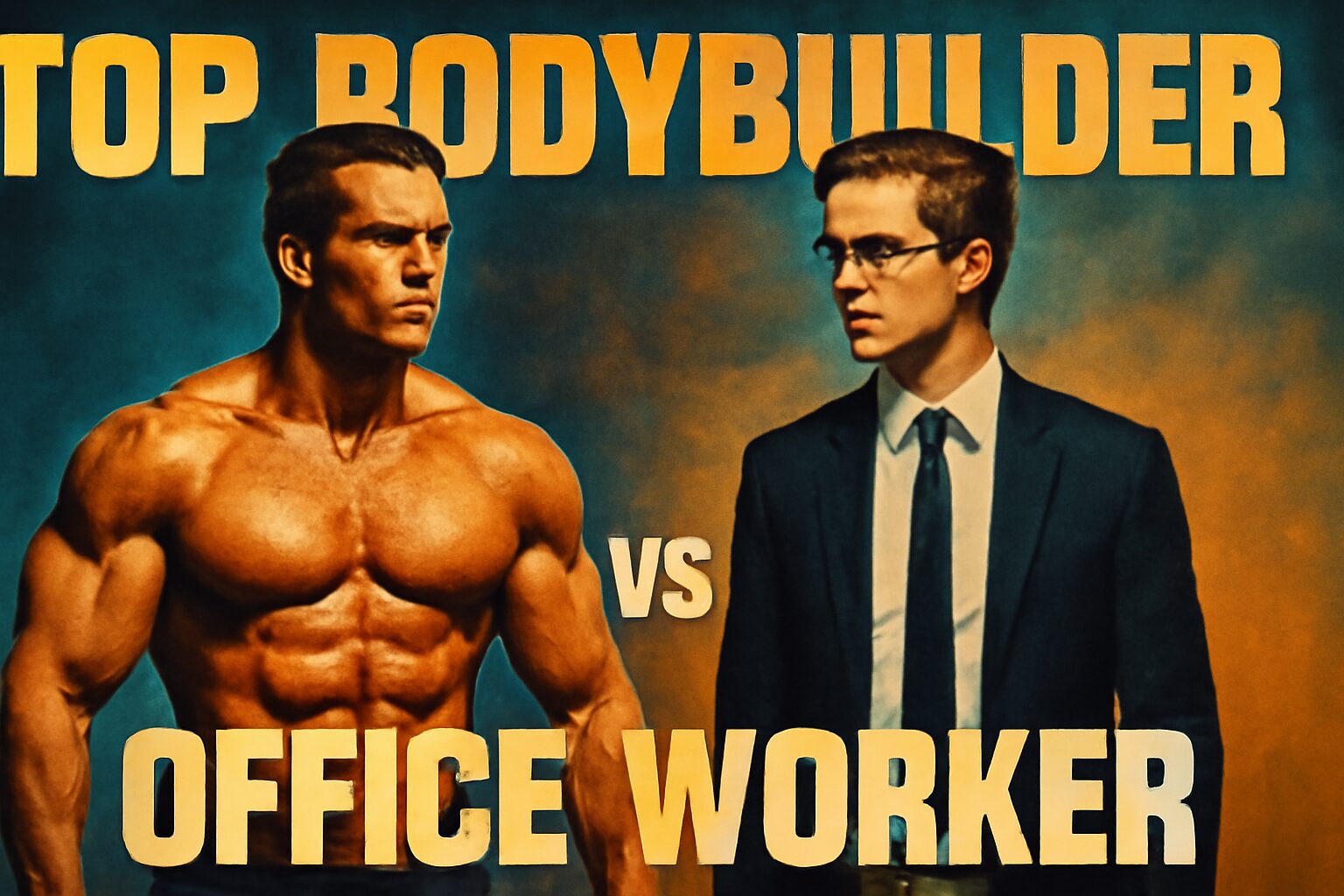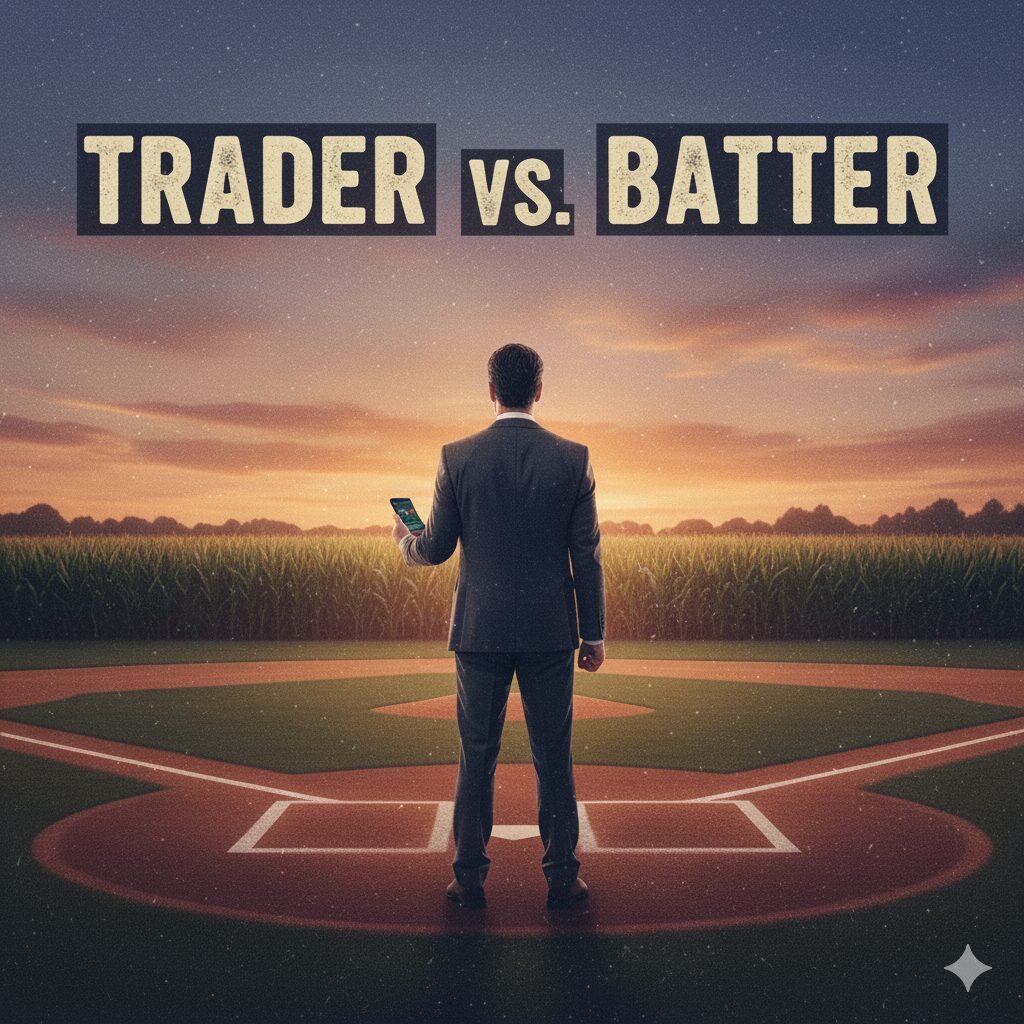終身雇用とリスペクト

終身雇用が奪う、敬意と成長 なぜ日本の職場には「リスペクト」が根付かないのか
最近、私の勤務先の銀行で足りないものを考える機会がありました。
そしてその答えとして、
特に上司から部下および同僚同士の
「リスペクト」だということに辿り着きました。
また、これまでの私の人生で、
例えば教師であったり上司または
経営者という周囲を導く立場にいる人たちから
「相手をリスペクトしなさい」という言葉を
聞いたことがなかったため、
これは私の勤務先に限ったことではないのではないか
という思いに至ったのです。
なぜ日本の企業文化に
「リスペクト」が育たないのかと考えた際に、
それは特に「終身雇用」という制度が、
知らず知らずのうちに私たちから
「敬意」と「向上心」という
2つの大切な価値を
奪っているのではないかというものでした。
“Respectus”という言葉に象徴される文化の差
私がかつて通っていたアメリカ・ニューヨーク州の高校の
卒業アルバムのタイトルが「Respectus」でした。
これは「Respect(敬意)」の語源ラテン語で、
「すべての人に敬意を払う」という学校の理念を象徴しています。
私が入学当初所属していた
ESL(English As Second Language)の先生は、
ことあるごとにこう言っていました。
「どんな人に対してもリスペクトを持つように。」
それは単なる綺麗事ではありませんでした。
アメリカでは、教師も経営者も、誰であっても
“他人に敬意を持つこと”を当たり前のように語ります。
しかしながら、私は日本でこれまで出会った
教師、経営者、管理職の中で、
同じように「リスペクト」について語る方は
残念ながら記憶にありまん。
終身雇用が生み出す“ぬるま湯”
日本の多くの企業では、
最近ようやく議論がなされているものの、
いまだに終身雇用が前提となっています。
つまり、一度入社すれば
良くも悪くも簡単には解雇されないという、
「守られた環境」です。
この「守られている」という安心感が、
「楽な仕事で給料もらえればいい」
という発想に繋がりやすいと感じています。
実際、私は同僚からこの言葉を何度も聞いたことがあり、
その度に違和感を持ったものです。
そこには、“他人に敬意を払う”とか
“自分の成長のために努力する”という思考が
入り込む余地がありません。
本来であれば、企業という組織に所属する以上、
「自分が成長しなければ組織に貢献できない」
という意識があってしかるべきです。
しかしながら、解雇されるリスクがほとんどないことが、
結果として「成長しなくても許される」
という慢心を育ててしまっているように思えてなりません。
私が受けた“人生観の教育”
そのESLの先生は、アイルランド系で、
毎週欠かさず教会に通う方でした。
彼女の教えには、キリスト教的な
「赦し」や「寛容さ」が根底にありました。
私に英語を教えてくれる一方で、
「すべての人に敬意を持つこと」、そして
「過ちを犯した人であっても、人としての価値を認めること」
を教えてくれました。
それはまさに、“英語の授業”の中に
人生観が詰まっていた時間でした。
私は当時つたない英語で
「Respect for all people, including for example criminals too?
(先生、全ての人に敬意を持つべきって、例えば犯罪者も含めて言われていますか?)」
と尋ねたことがあります。
すると彼女は、
「Yes, all people, including those who did something wrong.
(そうよ。犯罪をおかしていようが、何であろうが、すべての人よ。)」
と答えてくれました。
私は特にどの宗教にも所属はしていませんが、その言葉は、
「人は誰しも完全に悪ではなく、すべての人に仏性がある」
といった仏教的な考えにも通じるものがあり、
私の中で深く印象に残っています。
自分と違う価値観を否定することは、自分の価値を下げること
このような価値観に触れてきた経験もあってか、
私は日本の企業文化の中で違和感を覚えることが多々ありました。
例えば、自分と違う意見や価値観を持つ部下に対して、
敬意を欠いた態度をとる上司がいると、
「この人は自分の成長を自分で止め、
自分の価値を自分で下げているのではないか」
と感じてしまいます。
極端な例ではありますが、
「人はどんな間違いを犯しても、すべてを否定されるべきではない」
という前提に立てば、
「自分と考えが違う」という理由だけで相手を否定したり、
軽んじたりすることが浅はかだと気づくはずです。
「それ、あなたの意見ですよね?」という常套句
これは私が勤務先で債権回収の業務にあたっていた際のエピソードです。
延滞者の対応をしていると約束の時間になっても入金しないどころか、
連絡すらしてこない方が非常に多くおられました。
お金に関しては、文字通り「ない袖は振れない」ので、
どうしようもない状況もあるかと思います。
しかしながら、時間は自分の管理や工夫次第で
いくらでも調整ができるはずですから、
「時間を守れない人はお金も守れない傾向にあります。
まずは時間の管理から行ってみたらいかがですか?」
とある延滞常習者の方にご提案したところ、
「それ、あなたの意見ですよね?」
と返されたことがありました。
一瞬、ひろゆきさんの影響を受けている方なのかな
とは思いましたが、そこは冷静に、
「私は一社員に過ぎませんが、一社員が意見をお伝えしては駄目ですか?」
といったやり取りがあったのを記憶しています。
アメリカであれば、意見を持たない人間のほうが信頼されません。
しかし日本では、会社に所属する一社員が
「主観」を述べることすら許されない空気感があります。
それこそが、会社内で「リスペクト」や「自己成長」が
育ちにくい文化を生んでいる一因なのではないでしょうか。
「敬意」と「成長」なくして企業の未来はない
アメリカ企業、特に世界で成果を上げている企業には、共通する文化があります。
それが、「互いに敬意を持って接すること」であることは、
世界的な名著『ビジョナリー・カンパニー』の
最後のパートにもはっきりと書かれています。
企業が持続的に成長するためには、
「社員への敬意を前提に組織が機能すること」が不可欠だと。
まとめ:変えるべきは制度ではなく、意識
もちろん、今の日本の制度を変えるのは
簡単なことではありません。
しかしながら、各人が意識を変えることは、
今この瞬間からでもできます。
「守られているから努力しなくていい」ではなく、
「守られているからこそ、チャレンジし続け、同僚に敬意を払う」
という思いを持つ人が増えれば、
日本の企業文化は少しずつ変わっていくはずです。
終身雇用が悪いのではありません。
それに甘える「心の構造」こそが、問題だと私は考えます。
あなたの職場に、リスペクトはありますか?
本日の名言
社員に敬意があるから、高いパフォーマンスを「期待する」。
高い基準と困難な課題を設定するのは、社員が基準を達成し、
課題に立ち向かうと信じているからだ。
突き詰めると、偉大な企業の社員が一貫して卓越した戦術の遂行を
成し遂げるのは、彼らにその力があると誰かが信じているからだ。
このような敬意から、あらゆる人に尊敬される企業が生まれる。
ビジョナリー・カンパニ
ーZEROゼロから事業を生み出し、偉大で永続的な企業になる
ジム・コリンズ、ビル・ラジアー 著